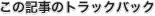前回の「夢十夜」ー「第一夜」異論の続きです。
自分はこう云う風に一つ二つと勘定して行くうちに、赤い日をいくつ見たか分らない。勘定しても、勘定しても、しつくせないほど赤い日が頭の上を通り越して行った。それでも百年がまだ来ない。しまいには、苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に欺されたのではなかろうかと思い出した。(太字は本文)
問題はこの男が女のメッセージをどのように受けとめたのかということですが、語られているのは、永遠の愛と復活の象徴で充たされた時空のなかで、男は女の依頼を従順に遂行しているということだけです。死んでも女は男に自分を忘れぬように様々な愛の象徴を用いて精一杯のメッセージを送っていますが、男はその意味を理解しているようにも見えません。100年が来るのをただ日を数えて待っているだけです。だから女に対する疑念が生じるのです。
すると石の下から斜に自分の方へ向いて青い茎が伸びて来た。見る間に長くなってちょうど自分の胸のあたりまで来て留まった。と思うと、すらりと揺ぐ茎の頂に、心持首を傾けていた細長い一輪の蕾が、ふっくらと弁を開いた。真白な百合が鼻の先で骨に徹えるほど匂った。そこへ遥の上から、ぽたりと露が落ちたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して冷たい露の滴る、白い花弁に接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず、遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。
「百年はもう来ていたんだな」とこの時始めて気がついた。
「すると」という接続詞があるように、男が「自分は女に欺されたのではなかろうかと」女の愛に疑念を抱いた瞬間です、突然石の下から茎がするすると伸びてきて、真っ白な百合の花が男の目の前で咲きます。そしてその花は「鼻の先で骨に徹えるほど匂」います。さらに空から「露」が落ちてきて、男は「露の滴る、白い花弁に接吻」するわけですが、注意しなければならないのは、男のこの接吻は男の内部では女と何も関連づけられていないことです。なぜなら男が「百年はもう来ていたんだな」と女の存在に気付くのは「暁の星」を見た時だからです。(「この時始めて気がついた」)
男が女への愛への疑念を抱いて「暁の星」が瞬くまでの結末までの一連の流れは、活字だとなかなかわかりにくいのですが、ものすごくスピーディーです。(アニメにでもしたらこの場面の印象はずいぶん変わるのではないでしょうか。面白いと思います)それに対し、ここでも男の気づきの遅さは対照的です。
この場面に登場する「百合の花」や「暁の星」も聖母マリア(純愛)の象徴であることは明らかです。この「露」は何かというと女の涙でしょう。なぜ女は涙を流したのか、それは男に女の愛への疑念が兆したからです。女はここでも彼女の愛の情念を象徴を通して強く訴えています。男に疑念が生じた途端、女は慌てて百合の花に化身して芽を出し、花を咲かせ、さらに「骨に徹えるほど」の芳香を放ち、「私はここにいるのよ」とばかりに強烈に自己の存在をアピールし、さらには空から「露」を落とし男に兆した疑念への悲しみを訴えます。男の疑念に対し、むしろ大いに焦った「人間らしい」女の姿さえかいま見えます。
死んで言葉を失った女は、様々なモノを通して切々と男への変わらぬ愛と復活を訴え続けてきたのですが、しかし残念ながら男は何も女のメッセージに気づいている様子はありません。女がこれでもかこれでもかと愛と自分の存在を訴えかけるのに対し、男は、最後に「暁の星」を見てやっと「百年はもう来ていたんだな」と女の復活に気づくのです。
この物語で際だっているのは、懸命に自己主張する女と、それに気付かない鈍感な男との意識の〈滑稽な〉すれ違いでしょう。男と女は愛し合っていないのではありません。ただ「愛してる」という女のメッセージが男に伝わらないだけなのです。私はこの二人の齟齬にこそ「第一夜」のメッセージがあると思います。
なぜ二人の意識がすれ違ってしまうのか。女は死ぬことで言葉を失い、代わりにキリスト教の象徴を通してその永遠の愛を伝えようとするのですが、男はキリスト教という精神文化を共有していないために女のメッセージがわからないからです。
このように「夢十夜」第一夜はロマンチィックな男女の愛の物語とは違うのではないか。これをどういうアレゴリーとして読むのかは自由ですが、すくなくとも永遠の愛のアレゴリーにしてはとぼけた話のようです。私はこの物語を、日露戦争に勝利して西洋化に成功し、一等国になったと有頂天になっている日本人を批判したアレゴリーなのではないかと思います。つまり西洋化に成功したと思いこんでいるが、西洋とのコミュニケーションはその深いところでは大きな亀裂があることに日本人は気づいていないということを揶揄しているのではないか、そういうふうに読みます。
横文字の思想家の名前を本のタイトルに並べてありがたがる風潮は、今になっても変わりません。これではロマンチィックな幻想譚が台無しですが、こう読めてしまったのですからしょうがありません。(高口)